公益法人経理担当者のためのローカルLLM活用入門
掲載:2025/10/16
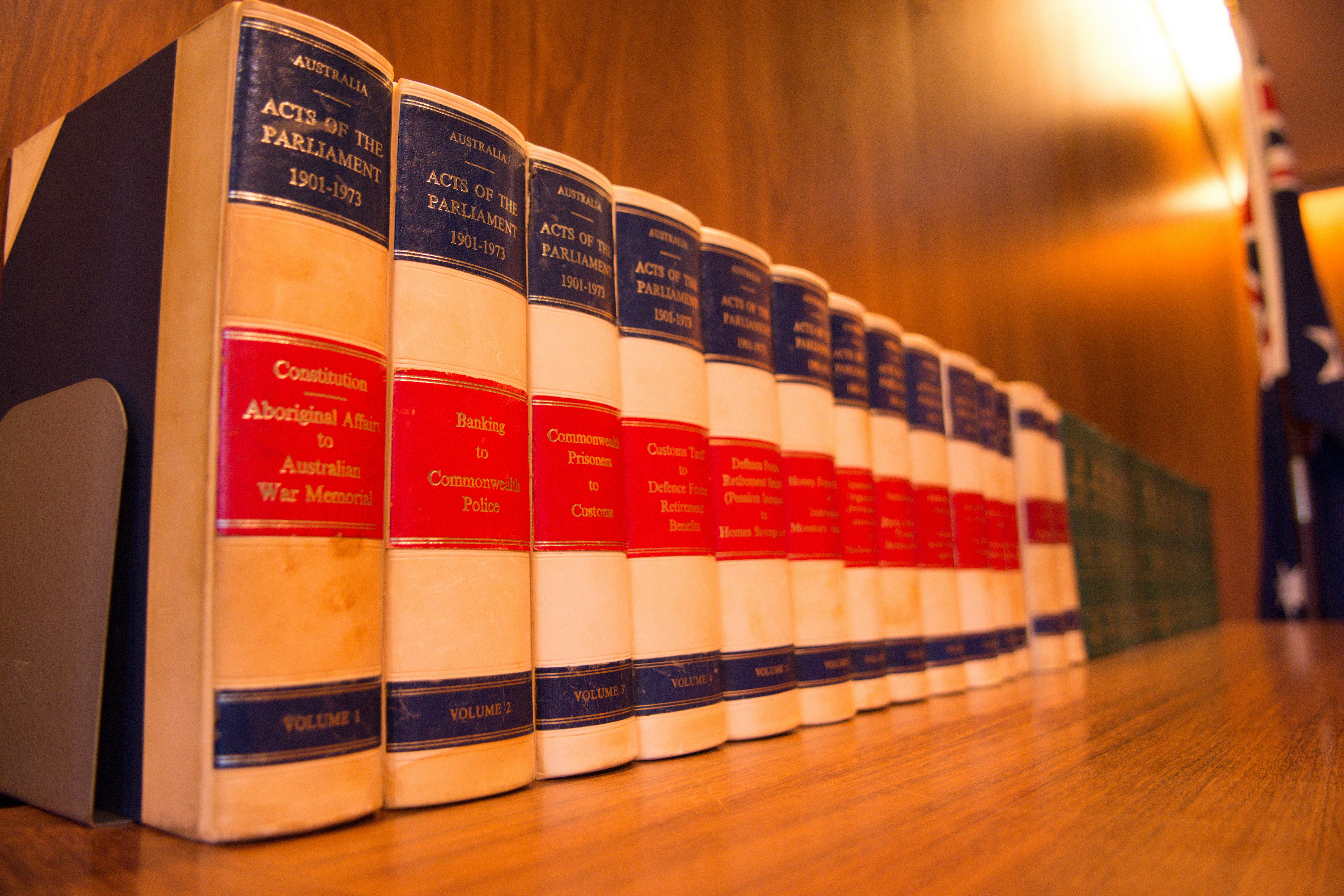
はじめに
公益法人の経理業務に携わっていると、日々の仕訳入力から決算処理に至るまで膨大な情報を正確かつ効率的に処理することが求められます。 特に謝金の支払いに関する実務や支払調書の作成業務は、税務上のルールに従って正確に処理する必要があるため、担当者にとっては大きな負担となりがちです。 Excelや会計システムを駆使しながら入力や確認を何度も繰り返すその過程は、ときに機械的でありながらもミスが許されない緊張感を伴います。
こうした背景において、近年注目を集めているのがローカルLLM(大規模言語モデル)の活用です。 ChatGPTのようなクラウド型のサービスが広く知られるようになったことで「生成AI」という言葉が一般的になりましたが、法人内に閉じた環境で動作するローカルLLMは、セキュリティやプライバシーを重視する経理業務において強い味方となります。 特に、外部に情報を出すことが難しい公益法人の経理現場においては、ローカル環境に導入したLLMを上手に使うことで、安全かつ効率的に業務を支援してもらうことができます。
本記事では、まずローカルLLMとは何かを丁寧に説明し、その特徴やメリットを整理します。 そのうえで、公益法人の経理担当者にとって馴染みのある謝金や支払調書の業務に焦点をあて、実際にLLMや関連技術であるRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)をどのように活用できるかを、五つの具体的なアイディアとしてご紹介します。
もくじ
ローカルLLMとは何か
LLMは「大規模言語モデル(Large Language Model)」の略称で、膨大なテキストデータを学習して自然な文章を理解・生成できるAIです。 ChatGPTを代表とするサービスが有名ですが、これらは基本的にクラウド上で稼働しており、利用者の入力内容が外部サーバーを経由するという性質があります。
一方でローカルLLMとは、その名の通り自分たちのPCや法人内のサーバーといったローカル環境で稼働させるLLMを指します。 これにより、入力データが外部に送信されることなく閉じた環境で処理されるため、セキュリティや情報漏洩のリスクを抑えつつ利用できるという強みがあります。
公益法人においては、外部に流出してはならない個人情報や内部資料を扱う場面が多いため、クラウド型サービスよりもローカル環境で動作させるLLMのほうが安心感があります。 さらに最近では、軽量化されたモデルが普及し、比較的低スペックなマシンでもLLMを扱えるようになってきました。
公益法人の経理業務とAI活用の親和性
経理業務は「数字を扱う」イメージが強いものの、その裏には膨大なテキスト処理が存在します。 例えば謝金の支払依頼書をチェックし、対象者や金額を確認し、適切な勘定科目に仕訳を切る作業だったり、支払調書の作成に際しては、源泉徴収の有無や所得区分を判定し法定調書に正しく反映させる必要があります。 こうした処理は細かいルールに則っているため人間の確認作業が欠かせませんが、同時に文章の解釈やルールの参照など、LLMが得意とする領域でもあります。
LLMはただの計算機ではなく、自然言語を理解して柔軟に対応できるAIです。 したがって「この謝金は講師謝金に該当するか」「源泉徴収すべきか」「支払調書の記載要否はあるか」といった判断に関して、適切な補助をしてくれる可能性があります。 もちろん最終判断は人間の担当者が行うべきですが、その前段階の整理や確認作業を大きく効率化することができる可能性があります。
謝金と支払調書をめぐる実務の課題
公益法人において謝金を取り扱う場面は多岐にわたります。 講師への謝礼、委員会の外部有識者への報酬、原稿執筆を依頼した際の謝金など、名称は同じでも実態はさまざまです。 そしてその処理方法も、給与所得に近いものなのか、雑所得に区分されるのか、はたまた非課税扱いできるのかといった判断が伴います。
さらに年末が近づくと、税務署に提出するための支払調書を作成する作業が待っています。 支払調書は、誰にいくら支払ったかを記録し一定の条件に該当する場合に提出義務が生じる重要な帳票です。 金額や区分の誤りは法人の信用に直結するため、担当者にとって大きなプレッシャーになります。
ここで感じるのは、単なる金額処理だけではなく「文脈を読み解き、ルールを参照し、適用する」という作業が多いという点です。 この部分こそ、LLMの支援が力を発揮できる領域なのです。
RAGという仕組みの可能性
LLMを業務に活用する際に欠かせない技術としてRAG(ラグ:検索拡張生成)があります。 これは、LLM単体に知識を詰め込むのではなく必要な情報を外部のデータベースや文書から検索し、それを参照しながら回答を生成する仕組みです。
例えば経理規程や税務マニュアルをRAGのデータベースに登録しておけば、担当者が「この謝金は支払調書に載せるべきか」と質問した際、AIは関連するマニュアルの条項を検索して提示しながら、わかりやすく説明してくれます。 これによりどこの情報をもとに回答したのかわからないブラックボックス的な回答ではなく、検索してほしいデータの中から得られた情報をもとに正しい回答を得られるようになります。

業務改善のための五つの具体的アイディア
ここからは、公益法人の経理担当者が直面する謝金や支払調書に関わる業務を念頭に、ローカルLLMとRAGを活用してどのような改善が期待できるかを、五つの具体的なアイディアとしてご紹介します。
一つ目は「謝金の支払依頼書チェック支援」です。 日々提出される支払依頼書をLLMに読み込ませ、対象者や支払理由が適切かどうかを確認させる仕組みを導入できます。 RAGで内部規程を参照させれば「この依頼は旅費に分類すべき」「これは講師謝金として処理可能」といった指摘を受けられます。 担当者はAIが指摘した箇所を重点的に確認すればよくなり、確認作業の効率化につながります。
二つ目は「源泉徴収要否の自動判定サポート」です。 謝金の処理で悩ましいのが源泉徴収の要否です。 LLMに対し「このケースは源泉が必要か」と尋ねると、関連する所得税法や国税庁のQ&Aを検索して根拠を示しつつ回答してくれるように設計できます。 これにより、担当者の判断負担を軽減し、誤りを減らすことが可能になります。
三つ目は「支払調書の作成支援」です。 年末の支払調書作成時には、膨大な取引データを参照しながら対象者を抽出する必要があります。 ここでLLMを活用し、「今年の謝金で支払調書対象となる取引はどれか」と尋ねると、要件を満たす支払いを抽出する支援をしてくれます。 人が一件一件チェックするよりもはるかに効率的になります。
四つ目は「過去処理事例の参照と説明」です。 公益法人では担当者が異動することも多く、過去の処理判断が十分に引き継がれていない場合があります。 LLMに過去の仕訳や支払調書の記録を学習させれば、「昨年度の類似ケースではこう処理した」という事例を示しながらヒントを得られます。 これにより処理の一貫性が保たれることが期待できます。
五つ目は「新人教育とOJTサポート」です。 経理に配属された新人職員にとって、謝金や支払調書のルールは複雑で理解しづらいものです。 LLMを教育用アシスタントとして利用すれば、質問に応じて具体的かつわかりやすい言葉で説明してくれます。 RAGを使えば法人独自の規程に沿った回答も可能です。 新人は日常的にAIに質問しながら学習でき、OJTがよりスムーズに進みます。
まとめ
公益法人の経理担当者にとって、謝金や支払調書の処理は正確性と効率性が求められる重要な業務です。 ローカルLLMやRAGといった新しい技術を取り入れることで、セキュリティを確保しつつ業務の負担を軽減し、判断の一貫性を保ちながら質を高めることが可能になります。
AIがすべてを代替するのではなく、人間の知識と経験を補い支える存在として共に働く。 そうした関係を築くことで、経理担当者はより安心して本来の役割に集中できるようになるでしょう。 謝金や支払調書という具体的なテーマを通じて、その可能性を身近に感じていただければ幸いです。
システム・ワークスはグループ会社の株式会社第一コンピュータサービスと共同して、AI(LLM)の研究をはじめAIにまつわるコンサルティングや実証実験(Poc)のご提案、システムの導入のお手伝いをはじめました。
支払調書・法定調書・謝金システムに強い株式会社システム・ワークスでは、会計パッケージ選定支援、システムコンサルティング、ソフトウェア構築サービス、データセンター運用サービス、ITとビジネスを駆使してお客様のシステムを成功に導くお手伝いをしています。ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
まずはシステム・ワークスにきいてみませんか!
ローカルLLMとRAGの謝金や支払調書への活用についてのご相談はこちらから